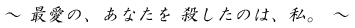風の強い日だった。
全寮制高校に通う由愛たちも、長期休暇の際には自分の家に帰ることが許される。冬休みに入り、家に帰ってきた由愛だが、ふと窓の外を見てぎくりとした。
窓の外を見ると、そこに一人の男がいたのだ。
男は何をするでもなく、ぽつんと家の前で立ち止まり、由愛の部屋のある二階を見つめていた。誰かを待っているように。昨今問題になっているストーカーかと思えるぐらい、その行動は不自然だった。
そして...彼の瞳と自分の瞳が...確かに合った――と思ったその時、ふっ、と突然、目に映る光景が変わる。
「なに......?」
呟いたその瞬間、言いようもない熱い感情がこみ上げてくる――
『キミ ハ ソコニ イルベキ ジャ ナイ』
頭に響く低い声。
見知らぬようで、でも懐かしい――
差し伸べられる手。
『私はあなたを知っている――?』
なぜかそう思った。
自分の思考に疑問を差し挟む間もなく、我に返ったときにはもう、そこに彼の姿はなかった。
何気なく自分の顔に手をやった由愛は、「え?」と小さな声を上げた。その手を自分の目の前にかざすと、濡れていることにはっとする。
もう一度確かめるためにゆっくりと指で自分の頬を撫で、初めて自分が涙を流していることに気づいた。
「なに、今の......何なの?――私、泣いてる?どうして?」
その問いは、風の音にかき消された。
* * * * *
冬休みに入って数日。
由愛は家でくつろいでいたが、あの、先日会った男のことが頭から離れなかった。
そんなもやもやを振り切るように、お気に入りの場所である、家から数分の公園に向かった。
「あれ?」
歩いているうちに、由愛は妙な違和感を感じて立ち止まる。
由愛はいつもと同じ、慣れた道を歩いているはずだった。いくら一年に数回しか帰らないとはいえ、何年も通ってきた道を間違えるはずがない。
なのに、何かが変なのだ。
何度も同じところを回っているような気がする。
そして、それは単なる由愛の思い過ごしではなかった。
――違和感。
――警告。
ぐにゃり。
――視界がゆがんだ。
本能的に目をつぶり、次に目を開けたときには――。
由愛は自分の目を疑わずにはいられなかった。
そこは、ギリシア神殿に近い造りの建物の中だったからだ。天井の高さと荘厳な装飾に圧倒される。
「な、なん......」
気が動転して何がなんだかわからなくなっている由愛の前に、一人の女性が姿を現す。
「お待ちしておりました。奥様。」
うやうやしく由愛の前に頭をたれる。その女性もやはりギリシア神話に出てくるような裾の長い衣装をまとっていた。
『奥様!?』
頭が上手く回らない。言っていることの意味が全く掴めない。
自分は今まで家の近くを散歩していたのに!?それが一転してこうだ。しかも普通の高校生の自分に目の前の女性は、由愛のことを『奥様』などと呼ぶ。
「な、なんかの間違いじゃないですか?あたし、誰とも結婚して、ないし......」
今問題にすべきはそんなことではないはずなのに、由愛にはそんなことしか言えなかった。
そんな由愛に目の前の女性は声高らかに笑ってみせる。
「やはり......、あなたはお忘れでいらっしゃいますのね......」
口元に笑みを残しつつ、女性は答える。
「......あなたは、誰......?」
由愛は呆然として聞き返す。一体何を自分は忘れているというのか。
「そうですわね......。この場合、私が名のるのが筋ですわね。」
妙に納得したように女性がにやりと笑う。
由愛はさっきから、生理的にこの女性に何かイヤなものを感じていた。好きとか嫌いとか......そんなものじゃ片付かない何か。
「私の名前はキエラ。あなたの前世でのお世話役、とでも申しましょうか?」
「前世......?」
由愛は繰り返した。
小説とか漫画ではよく読んだ話。
話としては面白くていいけれど、でもそんな話現実には考えられないと思っていた。だから、今そんなことを言われても信じられるわけがなかった。
「何言ってるの?頭おかしいんじゃない?」
懸命にそれだけ言葉をつむいだ。
そんな由愛のなけなしの努力もたいしたことではないというように、この女性――キエラは一蹴した。
「そう思いたくなる気持ちもわかりますわ。でも、これが現実。あなたは今全ての前世の記憶を失っている――。」
そこでキエラは一呼吸置いた。由愛の目をまっすぐ見据える。
「でも、あなたにはどんなことをしても思い出してもらわなければなりません。わが君、レスマドリアンさまのために」
そう、女が口にした途端、由愛は宙に浮いていた。