アルカディアスは数ヶ月前、セレニクル山の山奥で一人倒れているところを、山菜取りに来たふもとの村の住民に助けられた。このセレニクル山は、ランドリア帝国の都であるプルヴァから北に遠く離れた場所にある、帝国中で一番高く険しいとされる山である。しかしその荘厳な姿から『神の山』として神聖視されていて、その山奥まで足を踏み入れるものは滅多にいなかった。そのセレニクル山のふもとには、サルクシアンという山の民が『サルクス』という村を作っており、アルカディアスを助けたのはそのサルクシアンの一人であった。しかしアルカディアスは、その時には既に自分の名前以外、年齢も、どこに住んでいたかも、何をしにこの山へ足を踏み入れたのかも思い出すことはできなかった。アルカディアスの立ち振る舞いの優雅さや言葉にも方言が混じっていないことからすると、『おそらく都から来た者ではないか』と皆は口をそろえたが、何しろ何も思い出せない以上、どうしようもないことであった。
村長はそんな自分を不憫に思ってくれ、嫁に行ってしまった娘の代わりにと、とてもかわいがってくれている。村の人たちも皆親切な人ばかりで、アルカディアスを見かけると気軽に声をかけてくれる。
しかしアルカディアスは、皆が親切にしてくれればくれるほど、心が痛んでしょうがなかった。
正体不明の自分。
よもや天涯孤独の身で、誰にも必要とされていなかったのか。
あるいは自分は罪人なのではないか? そんなことまでが頭をよぎる。だとしたらここの人たちにこんなに温かくしてもらえるような身ではない。
アルカディアスは、いつも出口のない闇の中で手探りで歩いているような気がしていた。この村の暖かさに癒されながらなお、孤独だった。
--------------------------------------------------------------------------------
「おはよう、アルカディアス」
朝------身支度を整え、1階に下りて行くと、村長が笑顔で迎えてくれた。齢60過ぎ。灰色の裾の長い服を着ている。その顔に刻まれた数本のしわは、生きてきた貫禄を感じさせる。それでいて彼に威圧感はなく、ただ穏やかに時を過ごしている、そんな雰囲気をかもしだしていた。彼の存在は、不思議と共にいる者をホッとさせる。
「おはようございます。ドル様」
アルカディアスは、村長のことをそう呼んでいた。本当は『ドルネイド=ダナクスク』という名前があるのだが、この村の人たちは親しみを込めてそう呼んでいるので、自然とアルカディアスもそう呼ぶようになっていたのだった。
「アルカディアス、今日はわたしは若い者たちと会合があって、昼間はこの家から留守にするから、後のことはムミナに任せてのんびり過ごしなさい」
ムミナ、というのはこの家に家政婦として来ている中年の女性だ。この家の隣りに住んでいる。ドルの妻がまだ存命だった頃から親交が深く、ドルの妻亡き後、自分から希望してドルの家のことをあれこれと世話をやいているらしい。ちょっと・・・・・・いやかなりダイナミックな体型と性格の持ち主である。
「おっはよう!さあさ、朝食が出来上がりましたよ?ん」
部屋の扉が勢い良く開かれ、明るく元気な声がその場に響く。 ムミナは二人の為に朝食を作ってくれていたのだ。ムミナはお盆からスープを取りテーブルに置きながら、アルカディアスに声をかけた。
「なぁに、相変わらず顔色悪いね?!若いんだからもっともりもり食べて血色よくならなきゃ!あんたはまずそのガリガリの体型をなんとかしなきゃねー。あたしみたいにふっくらしなきゃさ!あたしゃ食欲旺盛。おかげで見るからに健康そのものでしょお」
からからと笑うムミナだが、アルカディアスは言葉に詰まってしまう。ムミナのことは嫌いではないが、どう対処していいか困ってしまうので苦手だ。
「こらこら、人にはそれぞれの限界というものがあるのだから」
ドルが穏やかにムミナをたしなめる。
朝食を食べ終わり、ドルが会合に離れの小屋に行ってしまうと、アルカディアスは途端に暇になる。同じ年頃の子達はこの時間は皆、この村では村外に働きに出るか、家の手伝いをしている。しかし、ドルだけが暮らすこの家では客人が来る時以外はやることもそうそうないし、ほとんどはムミナが一人で済ましてしまう。のんびりペースのアルカディアスにはムミナのスピードについていけず、たまにできる時にちょこっと手伝う程度だ。
今日も手伝うことはないかとムミナに聞いてみたのだが、「アルカディアスは休んでて大丈夫よ」と一蹴されてしまったため、やはりやることはなさそうだった。アルカディアスはいつものお気に入りの場所に出かけることにした。

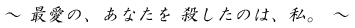
![[挿絵]2章(2)](http://umias.net/words/arcadia/img/sasie/2-2.jpg)
